本書將研究範圍界定在日本、臺灣、俄羅斯,以此三國間的文化交流歷史及諸多面向之實證探究為主要課題,從而檢視各自之相互認識、相關關係及其變化。
具體而言,主要探求的是與前述三國相關之人事物,尤其是曾造訪日本統治下的臺灣的俄羅斯人之事蹟,進而闡明三國之間的文化連結。例如,俄羅斯之東洋學者、民族學者涅夫斯基(Nikolai Aleksandrovich Nevsky)的臺灣原住民族研究即為一例。其研究不僅聚焦原住民族,同時牽繫起同一時代的日本、臺灣、俄羅斯,研究內容可謂與三國間的歷史環境、文化史脈絡密不可分。因此,毫無疑問地,其研究亦可進一步解讀為三國交流下的成果。
本書藉由探究、解讀此類事例以解析闡明以往在日俄交流史、日臺關係史的區別下未曾涵蓋的歷史相關性與交流多面性,並提示「全球視野下的亞洲交流史研究」此一新議題。
本著は日本・台湾・ロシアを研究範囲に定め、三国間の文化交流の歴史、およびその諸側面の実証的探究を中心課題とし、それぞれの相互認識、相関関係とその変容の検証を試みている。
具体的には、三国に関連した人物、出来事、事象、特に日本統治下の台湾を訪れたロシア人の事跡を追求し、そこから三国間の文化的連環を明らかにした。例えば、ロシアの東洋学者、民族学者ネフスキーの台湾原住民族研究。それ研究は原住民族のみならず、同時代の日本・台湾・ロシアを取りまいた歴史的環境、文化史的文脈とも密接不可分で、まぎれもなく三国交流がもたらした成果としても読み換えられる。
こうした事例の探究と解読を通して、従来の日ロ交流史や日台関係史の区分には収まらない歴史の相関性、交流の多面性を解明し、「グローバルな視点で見るアジア交流史研究」の新しい試みを提示する。
作者簡介:
塚本善也(つかもと ぜんや)
早稻田大學文學研究科俄國文學專攻。博士(文學)。中國文化大學日本語文學系副教授。專長為日俄台之比較文化、文化交流史。著有《音樂家江文也與日本》、《台灣原住民族鄒族指導者的時代及其生涯:高一生研究》、〈葉理謝耶夫之台灣訪問相關考察:以《福爾摩沙報告》為線索〉(《天理台灣學報》第27號)等著作、論文。
早稲田大学文学研究科ロシヤ文学専攻博士(文学)。中国文化大学日本語文学系副教授。専門は日ロ台の比較文化、文化交流史。主な著書・論文に『音楽家江文也と日本』、『台湾原住民族ツォウ族の指導者の時代とその生涯―高一生研究―』、「エリセーエフの台湾訪問をめぐる考察―『フォルモサ報告』を手がかりとして―」(『天理台湾学報』第27号)など。
章節試閱
序章(抜粋)
一、研究課題・問題設定
日本、ロシア、台湾の三国間にはかつてどのような交流があったのか。それはいかなる歴史的環境、世界史的文脈のもとで起きたのか。
この問題意識のもとに、三国に関わる出来事や人物、特に日本統治下の台湾を訪れたロシア人に注目し、これまで顧みられることのなかった交流の軌跡を検証し、そこから浮かびあがる日本、ロシア、台湾の連環を明るみにすること。本書はこうしたことを研究課題とする。
周知の通り、日ロ間、日台間には多方面で長く複雑な歴史がある。第二次大戦までを大まかに振り返っても、次の出来事があげられる。
国際関係は友好的なものばかりではない。たとえば、日本人のロシアに対する不信感やいわゆる「恐露病」は今日でも根強い。1891年の大津事件で、来日中の皇太子ニコライを切りつけた巡査津田三蔵の返答はその一例である。凶行理由を問われ、津田はこう答えたといわれる。
露国が我が日本国に交際するや樺太交換以来日本国より彼れ露国を利することあるも彼れ露国より我が日本国を利したることなく、古来我が日本国を横領せんとする露国その皇太子は、我が日本国の地理地形を視察し他日横領せんとせらるる便宜に供するため御来遊になりたるものなりと信ず。もしこのまま露国皇太子殿下を生かして御還し申せば他日必ず我が日本国を横領に来らるる御方なるを以て我が国のためやむをえず露国皇太子の生命を戴かざるを得ざる次第なり。(波線引用者)
このような脅迫観念、感情的な偏見にとり憑かれたのは津田のみではなかった。幕末の駐日イギリス公使オールコック(在1859-1864)は、大津事件のはるか以前にこう指摘していた。日本人は諸外国からの武力行使はないと高をくくりながらが、「ロシアだけは例外だ。日本人は、ロシアを本当に恐れている」、と。
しかし、明治以降、日本人がロシアの文学に学び、芸術を享受してきたことは、まぎれもない事実である。ロシア通で知られた、明治のジャーナリスト大庭柯公(1872-?)はこう書いている。
けだし露人は科学の民に非ずして芸術の人なり。文学見るべく、絵画賞すべく、音楽聴くべし。プーシキンが「我らの生まれしは真に感興のためなり、いみじき音響のためなり」と言いたりしは、露人を語り得て余地なきものに似たり。
芸術のみならず、教育・学術、スポーツ、衣食文化など多方面で、亡命ロシア人(白系ロシア人)が日本(文化)にもたらした影響も見逃せない。
ロシアの対日観もやはり一様でない。たとえば、19世紀末ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世が鼓吹した「黄禍論」は、ロシア皇帝ニコライ二世に深甚な影響をもたらし、それが三国干渉、日露戦争開戦につながったともいわれる。アジアに対する潜在的恐怖はヨーロッパにそれ以前からあったが、ロシアは過去にモンゴルに支配された経験(「タタールの軛」)を持つだけに、そうした恐怖感は根強かった。
しかし、それにもかかわらず、日本への関心が失われることはなかった。19世紀後半から20世紀初頭にかけて起きた「ジャポニズム」はその一例である。もちろん、好奇心は恐怖心の裏返しともいえるが、日露戦争の敗北後もロシアでは日本の芸術への関心はむしろ高まったとさえいわれる。
それでは、日台関係はどうか。ひと頃、現代日本の大衆・流行文化を好む若い世代を意味する造語「哈日族(ハーリーズー)」がはやったように、台湾が親日的とはよくいわれる。事実、財団法人日本台湾交流協会による『2018年度対日世論調査』で、日本は第二位の国を大きく離して「最も好きな国」と回答された。逆に、日本人にとっての台湾は、2017年の台北駐日経済文化代表處の調査で、「アジアの中で最も親しみを感じる国」であった。
だが、そうした良好な関係は常に不変的にそうであったわけではない。かつて日本軍が蒋介石(1887-1975)率いる国民党軍と戦火を交えたことを想起するなら、今日の変化は劇的とさえいえる。また1972年の日華国交断絶は二国関係を大きく転換させ、その結果、台湾の「台湾史研究は抗日抵抗史が全てであった」といわれる時期をもたらした。それゆえ、そうした過去を知らずに、今日の日台関係の意義深さは理解できないのである。
それでは、ロシアと台湾の間にはどのような歴史があるのであろうか。ロシア人の台湾上陸を記したものに、まず『マウリティウス・アウグストゥス・ド・ベニョフスキー伯爵の回想・旅行記』(1790年)がある。そこには、ベニョフスキーに随伴してカムチャッカを脱出した元イズマイロフ近衛連隊大尉ステパーノフらロシア人数名が登場する。水口志計夫によると、「ベニョフスキーのロシア人の仲間は、一八世紀において彼らの前後のどのロシアの航海者よりも太平洋を遠くまで航行し、またほとんど世界を一周した最初のロシア人となった」。そうだとすると、彼らこそ台湾上陸をはたした初のロシア人であったかもしれない。ベニョフスキーの書はヨーロッパで広く知られたにもかかわらず、ロシアでは日本に関する箇所は長く忘れられていた。台湾情報も推して知るべしで、彼は資源豊富な島を獲得すべきと主張したが、ロシアが目を向けることはなかった。
19世紀に入り、欧米列強による植民地獲得競争は台湾も呑みこんでいった。1856年のアロー号事件後、天津条約(1858年)が結ばれると、清朝政府は1862年に滬尾(淡水)、安平の開港を認め、以後雞籠(基隆、1863年)、打狗(高雄、1864年)を開放し、イギリス、フランス、プロシア、アメリカの船が入港することとなった。イギリスは商社怡和洋行(Jardine, Matheson & Co.)、顚地洋行(Dent & Co.)がいち早く業務を開始し(1858年)、1861年には領事館を設立した。フランスもプロシアもそれぞれ開港地で交易活動を始めた。それに対して、ロシアは日露和親条約締結後(1855年)、列強とともに天津条約に連なりながら、その後の行動は鈍かった。活発な通商関係を進める様子は見られず、明らかに台湾進出に積極的でなかった。
時代は下り、1949年10月3日ソ連は中国共産党政府を承認した。そのため、国民党政府はソ連との外交関係を断交し、長く親米反共政策を外交の基軸に掲げた。その後、直接の通商、国家レベルの交流が再開されたのは、ようやく1990年2月である。1992年には両首都に経済文化協調委員会代表處を設置することで合意した(93年駐モスクワ、96年駐台北代表處設立)。以後、多方面で協力関係が築かれ、ロシアの学術界では90年代は「台湾発見の年」といわれるくらい活発な展開が見られた。2002年7月27日には、ロシアとの民間交流組織「台湾ロシア協会」が設立された。記念式典には陳水扁総統(当時)も出席し、今後ロシアとの関係を強化し、政党や議会間、文化、学術面の外交を促進していくと語った。またRadio Taiwan International(2008年2月20日)は、プーチン大統領(当時)が台湾を「国家」と呼び、台湾の急速な経済発展を称賛したと報じた。こうして、両国は正式な外交関係にないものの、実務レベルで盛んに交流を進めている。
以上のように、各二国間にはそれぞれの交流の歴史があり、それに関する文献は膨大な数にのぼる。では、三国についてはどうか。これまで日ロに加えて中国、あるいは朝鮮(韓国)の三国に注目する研究はあっても、日ロ台に着目したものはない。しかし、21世紀の今日、世界中から東アジアに向けて関心が集まる中、この地域でロシアや台湾との関係を考慮外に置くことはありえない。それだけに本書の研究は先駆的かつ有意義なものとなるはずであるが、本書が注目するのは特に三つの国に視野を拡張するからこそ明らかとなる事象である。つまり、二国間に照準を定めていた時には気づかなかった歴史の側面、三国の連環から見えてくる諸相、交流の動態である。日本統治下の台湾を訪れたロシア人の行動や仕事こそ三国を結ぶ鎖ともいうべきもので、本書はそれらを追求することにより、従来看過された史実の新たな側面を照射していく。
二、研究の対象・方法
歴史は正史に記された大事件によってのみ築かれるのではない。文字記録のない交流についても、今日日本では多彩な分野で検証されている。そこには、旧来の「孤立した島国日本」という虚像への反省と打破が反映されている。たとえば、「環日本海」や「環東シナ海」といった海洋を交通圏と捉え、東アジア地域の《ヒト・モノ・情報》の流れを超域的に見ようとする研究がそれである。
17世紀後半に著わされた郁永河『裨海紀遊』には、台湾で毎年五、六十万両の甘藷が栽培され、日本やルソン島などへ出荷されたという記述がある。また、先のベニョフスキーは、「台湾の住民の唯一の商業は、ここに立ち寄る、何隻かの日本のバークと、シナ人とのあいだのものである」と記している。地理的な近さを考えれば、双方の住民間で日常的な往来があっても驚くにはあたらない。
北方でも同じことがいえる。環オホーツク海には「オホーツク文化」と呼ばれる古代文化圏があった。北海道のオホーツク海沿岸にも発見されたその古代遺跡は、アムール川(黒龍江)地域とつながる文化の流入を物語るという。サハリンの原住民族ニヴフ(ギリャーク)を通じて北海道の一部は、大陸との交易・交流圏に入っていた。アイヌの存在も無視できない。彼らは、かつて北はサハリンからアムール川の上流、南は東北北部にまで交易活動を展開し、南北を結ぶ担い手の役割をはたした。その活躍ぶりは果敢で、13世紀後半にモンゴル元軍がサハリン島のアイヌを襲来したほどであったといわれる。
日本が「絶海の孤島」でないのと同様、台湾をそう思いこむことも誤った通念である。そうである以上、三国を結ぶさまざまな事象に注目しようとする本書の試みは、ないものをひねり出そうとするものではないし、決して気を衒おうとするのでもない。
ただし、有史以前からの長大な時間、広大な地理的範囲、そして多様な分野をくまなく射程に入れることは不可能で、本書はごく局限された対象にとどまる。そこで、課題の検討に際し、研究対象を以下のように限定しておきたい。
イ)時期
本書は、日本が台湾を領有した1895年から1945年までを主要対象時期とする。
日本と台湾が最も特殊な関係にあったのはこの時代で、重要な事例にはこと欠かない。またロシアからはこの時期に亡命ロシア人を含め、さまざまな人が日本と台湾を訪れた。彼らが日本に残した痕跡はきわめて大きかった。同規模の痕跡を台湾に見出すことは難しいにしても、それでも見逃せないケースは少なくない。
1945年以後は相互関係が劇的に変化し、容易に論じられないこともあって除外した。たとえば、国民党政府の反共政策を検討することは、戦後台湾の対ソ関係を見る上で重要である。またソ連邦崩壊後、国際関係が大きく変容する中で、ロシアと台湾が官民両面でいかに関係構築を図っているかをたどることも大切である。しかし、現在進行中の二国間関係を正確に把握し、さらにそこに日本を位置づけるには、ある程度歴史的回顧的にふり返る時間の経過を必要とする。時間的距離を以って三国を貫く歴史を見きわめることが可能で、かつ本書の研究課題に対応する事例はまさに日本の台湾統治時代に見出される。
ロ)検討対象
何らかの形で三国に関わり、《関係/交流》史上の諸相を開示する対象として、特に日本統治期に台湾を訪れたロシア人を取りあげる。全章の主役が彼らであるわけではないが、ここでなぜ「人」であり、ロシア人なのかについて説明しておきたい。
異なる社会や主体間の交流はさまざまな角度、分野でたどることができる。種々の産業部門、芸術、学術、宗教、科学、スポーツ、日常生活等々で、また目的と方法によってアプローチする面はいくらでもある。中でも戦争を含む国家同士の外交関係はその最大のものといえよう。しかし、個々の人間に着目するのは、それがまさしく特殊な経験であるからに他ならない。ここで特殊というのは、異例、例外という意味ではなく、唯一性・固有性を帯びた経験のことである。歴史が反復されるものか否かはともかく、本書は、個人の経験は一回きりであり、そこにこそ一般化し得ない「歴史」があると考える。
ひとりの人間がなぜ異文化世界へ出かけ、そこで何を見聞し、どう受け止めたのか。それはいわば他者との出会いであり、その経験は国家同士のそれに還元できない個人的個別的なものである。国家的偉業とは異なる次元での他者との出会いは、大文字の出来事ではなくても、日ロ台三国が交差した瞬間、交流の側面であって、そこに本書は一回性の歴史/歴史の一回性を見ていきたい。
本書で着目するロシア人が台湾へやって来て、出会った異文化は台湾のみならず、日本でもあった。それゆえ三国の関係、交流の諸事象を検討するのに、日本統治時代の来台ロシア人はケーススタディに恰好の対象であり、彼らに焦点を据えることは、日本と台湾を同時に視野に入れることを可能とする。本書の研究課題の解明にそれは最も近道であると考える。
そうした事象に着目するにあたり、本書が取る方法、視点について記しておきたい。ただし、あらかじめ断わっておくと、各章の対象は互いに分野も時代も異なるので、方法もそれにより変わらざるを得ない。したがって、細かな説明は各章で行う。
本書の基本作業は、各章の人物が書き残した文書、書物や、出来事に関する文献、記録類の解読、分析である。そして彼らが空間移動し、残した仕事がどう三国と関わるかを明らかにするために、それぞれの時代に三国を取りまいた種々の文脈を参照する。その文脈とは、大きく捉えれば、各国の政治的社会的文化的環境であり、公的私的を問わず、関連資料、文献からそれをたどる。範囲をしぼって見れば、各人物に関わる分野の研究史(博物史、宗教史など)や、渡航した当時の状況もその文脈となる。
序章(抜粋)
一、研究課題・問題設定
日本、ロシア、台湾の三国間にはかつてどのような交流があったのか。それはいかなる歴史的環境、世界史的文脈のもとで起きたのか。
この問題意識のもとに、三国に関わる出来事や人物、特に日本統治下の台湾を訪れたロシア人に注目し、これまで顧みられることのなかった交流の軌跡を検証し、そこから浮かびあがる日本、ロシア、台湾の連環を明るみにすること。本書はこうしたことを研究課題とする。
周知の通り、日ロ間、日台間には多方面で長く複雑な歴史がある。第二次大戦までを大まかに振り返っても、...
目錄
序章
一、研究課題・問題設定
二、研究の対象・方法
三、本書の構成・内容
第一章 パーヴェル・イビスと「フォルモサ紀行」
はじめに
一、イビスの経歴と「フォルモサ紀行」のテキスト
二、イビス来台の背景―「台湾出兵」
三、イビス来台の目的と台湾調査
四、イビスのまなざし
小括
第二章 博物学者モリトレフトの台湾調査
はじめに
一、モリトレフトの経歴と仕事
二、来台の背景①―19世紀博物学史概観
三、来台の背景②―抵抗と安定
四、調査ルート、日程および目的と結果
五、モリトレフトのまなざし
小括
第三章 大主教ニコライと日本ハリストス正教会による台湾伝道
はじめに
一、台湾における宗教事情概観
二、ニコライと台湾伝道論議
三、台湾伝道者について
四、在台日本人信徒とロシア人
五、在台正教会をめぐる諸問題
小括
第四章 ネフスキーから見る日本と台湾―『ツォウ語方言資料』を中心に―
はじめに
一、台湾およびツォウ族を取りまく歴史的社会的状況
二、『ツォウ語方言資料』をめぐって
三、『ツォウ語方言資料』のテキストの「注釈」
小括
第五章 音楽家の出会い/文化の交通―チェレプニンと江文也―
はじめに
一、江文也―出会い以前
二、チェレプニン―出会い以前
三、チェレプニンの日本訪問
四、江文也とチェレプニンの交流をめぐって
五、チェレプニンの仕事、教え
小括
最終章
付録『ツォウ語方言資料』;テキストの翻訳
参考文献
あとがき
人名索引
事項索引
序章
一、研究課題・問題設定
二、研究の対象・方法
三、本書の構成・内容
第一章 パーヴェル・イビスと「フォルモサ紀行」
はじめに
一、イビスの経歴と「フォルモサ紀行」のテキスト
二、イビス来台の背景―「台湾出兵」
三、イビス来台の目的と台湾調査
四、イビスのまなざし
小括
第二章 博物学者モリトレフトの台湾調査
はじめに
一、モリトレフトの経歴と仕事
二、来台の背景①―19世紀博物学史概観
三、来台の背景②―抵抗と安定
四、調査ルート、日程および目的と結果
五、モリトレフトのまなざし
小括
第三章 大主教ニコライと日...
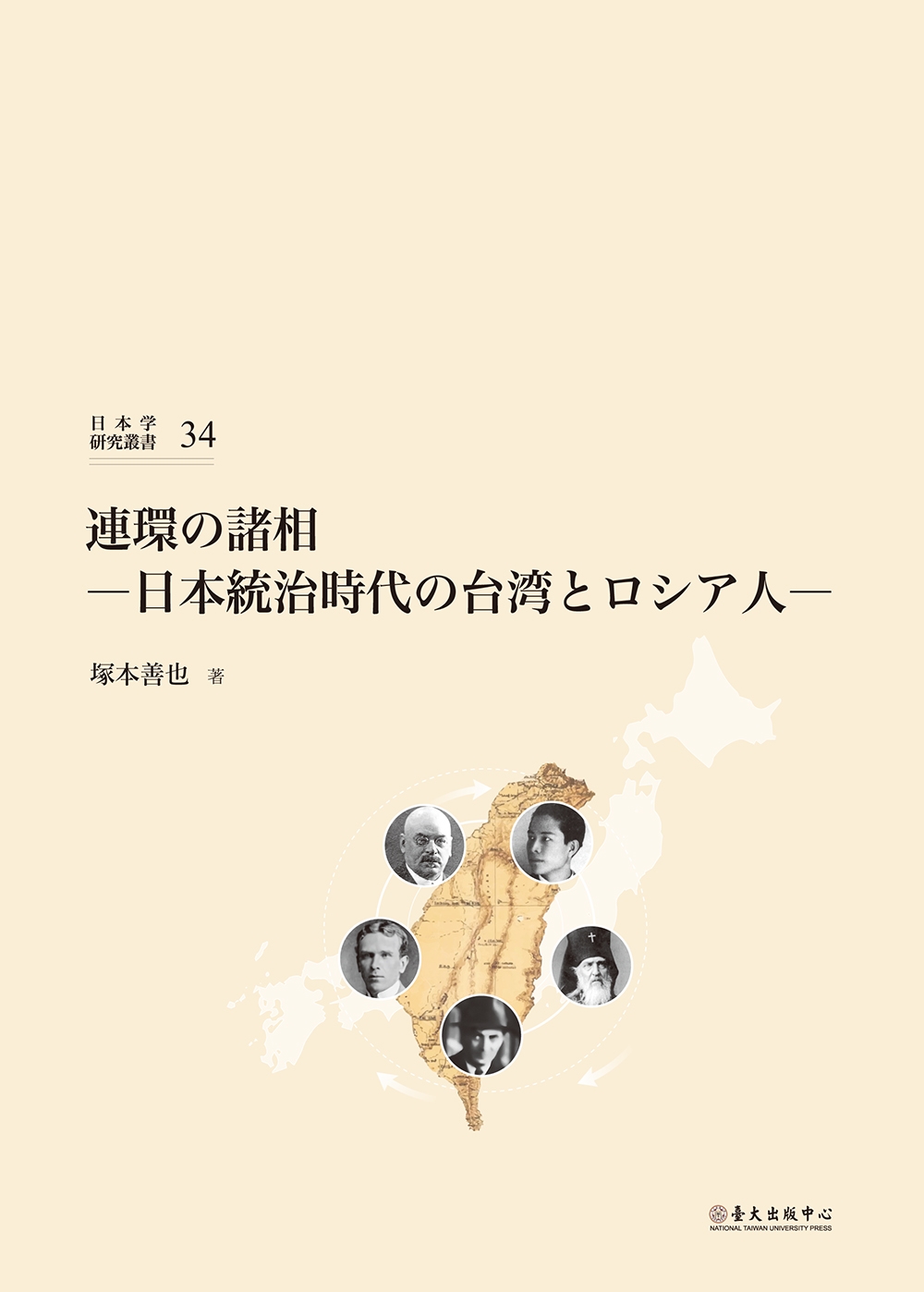
 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹
共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹










